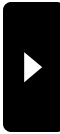2016年07月30日
バイクのユーザー車検に行ってきました 神奈川陸運支局ガイド
今日は午後からTAKUのピアノの発表会なので会社を休みました。
折角休みをとったので午前中にバイクのユーザー車検を通してきました。

私自身はこのバイクで6度目のユーザー車検になりますので流石に慣れました。
これから初めてユーザー車検を受けるという友人に詳細にレポートをアップするよう要請されておりますので詳細情報を入れるようにします。
友人も同じ神奈川陸運支局に行くとの事ですので今日の私の足跡をそのままレポートしたいと思います。
ユーザー車検をやってみようと考えている人に少しでもお役に立てたら嬉しいです。
では神奈川陸運支局に行ってみましょう~
折角休みをとったので午前中にバイクのユーザー車検を通してきました。

私自身はこのバイクで6度目のユーザー車検になりますので流石に慣れました。
これから初めてユーザー車検を受けるという友人に詳細にレポートをアップするよう要請されておりますので詳細情報を入れるようにします。
友人も同じ神奈川陸運支局に行くとの事ですので今日の私の足跡をそのままレポートしたいと思います。
ユーザー車検をやってみようと考えている人に少しでもお役に立てたら嬉しいです。
では神奈川陸運支局に行ってみましょう~
とその前に予約が必要です、ネットから簡単に予約できますのでそこからスタートですね。
1.継続車検の予約
・神奈川陸運支局のHPにアクセスする。
・左のメニューの検査手続きをクリックすると
検査の予約は自動車技術総合機構の予約システムからをクリックして予約システムに飛んでください。そこで新規アカウントを作って(簡単な手続き)検査を受ける日の予約を入れます。予約が完了すると予約システムから予約番号が書いてあるメールがくるのでそれをプリントアウトしてもって行きましょう。
【当日必要なもの】
・車検証
・自動車税納税通知書/領収書
・自賠責保険の証書
・点検整備記録簿(バイク購入時に冊子でもらえました なければこちらのリンクからダウンロードできます)
・上記を挟んでおくバインダー(書類を持って回るのであると便利)
・工具(ちょっとした修正ができるくらいのもの)
・印鑑(変更などがあった時の為 使ったことはない)
・現金
・予約システムから送られてきたメールをプリントアウトしたもの
2.神奈川陸運支局へGO
そしていよいよ出発です。
書類を揃えて記入してから受付するので受付終了時間の30分前には到着すると良いでしょう。
初めてなら1時間前くらいについているとゆとりをもって望めます。

適当な場所にバイクを駐車して③の建物に向かいましょう。
門を入って右側に建物が並んでおり③とビルに書いてありますので迷いようがありません(w

3.自賠責保険の更新手続き
③の建物の右下に代書と書いてある窓があります。
このスペースが自賠責保険の窓口もやっています。

ここで自賠責保険を2年延長する手続きを行い保険証をバインダーに挟んでおきます(受付時とか何かと確認されます)。
あくまで私のルーチンの紹介をしています。敷地の外にも沢山代書屋、保険窓口がありますのでお好きなところでどうぞ。
因みに書類の記入(代書)もやってくれます、2,500円くらいだそうですが継続なら自分で簡単にできますのでチャレンジしましょう。
ここで掛かった費用自賠責保険代13,640円
4.書類と印紙の購入
次に③の建物の右のほうの入り口から入ります。

ここで印紙を購入します。

ここで掛かった費用は
重量税印紙:4,600円
検査登録印紙:400円
審査証紙:1,300円
--------------------------------
合計:6,300円 (大型バイクの場合)
印紙を購入したらその左側の受付窓口で下記の用紙セットを購入します。
この3枚1セットで20円です。
・自動車検査票1(表)/自動車検査票2(裏)
・自動車重量税納付書
・継続審査申請書
今回は次の車検用に事前に記入してスムーズに臨めるようにと書損じたときの為に5セット購入しました。
費用は20円x5セットで100円です。
これ以外の費用は発生しません。
大型バイクのユーザー車検でかかる費用の合計は19,960円です。
通すだけなら最低この金額で通せます(用紙の予備は無で)。
③の建物には印紙を濡らすスポンジが置いてありますのでここで印紙を貼ってしまうことをお勧めします(他の建物だとツバつけて貼るしかない)
自動車検車票1の右の手数料納付書の下のマスに1,300円の印紙と400円の印紙を貼り付けます。
自動車重量税納付書の下のほうに4,600円の印紙【4,000+600)を貼り付けます。
(貼る組み合わせを間違えないように注意、印紙のレシートに金額の内訳があるからそれを見ながら貼りましょう)
5.納税証明
このあと2年前は③の建物の左側にある④の建物に入って自動車税の納税証明確認をしてもらうルーチンがありました。
今回④に入って納税通知書と領収書を窓口に出したところ 去年からこちらでは行っておりません継続審査受付で提出してください。と言われてしまいました。
もう④に来なくていいんですね~ 一つ工程が省けて得した気分です。
6.継続検査受付
そしていよいよ継続検査の受付のある②の建物に向かいます。
③の建物のトイメンの80mくらい離れたところで写真の右奥の2階建です。建物の上のほうも②とありますね。

ここで購入した3枚の用紙に必要事項を記入して受付を行います。
記入スペースに記載例が書かれていますので迷う部分はないと思います。
基本現行の車検証の記載内容を転記する(車体番号とか登録番号とかetc.)。
走行距離を記入する部分があったので予め調べておきましょう。
・自動車重量税納付書

記入例を見ながら書けばOK
今は詳しく解説されているブログが多くて助かります。こちらなど大変参考になります。
・自動車検査票1(表)

走行距離記入する箇所あります。
車検証と記入例を見ながら記入しましょう。
この一枚は後程検査ラインで合格の際にスタンプを押す用紙となります。
自動車検査票2(裏)

これも車検証に記載されている部分を記入すればOKでした。
ホイールベースの値、タイヤの大きさなどは空欄で出しましたが何も言われおりません。
・継続審査申請書

記入例を見ながら書けばOK
鉛筆書き指定のところがあるのでボールペンで書かないように・・・
記入するのに慣れないと30分くらいは掛かってしまいますので早めに到着したほうがよいですね。
家で記入していけば更に楽になりますので2年後の為に用紙は2セット以上買っておきましょう。
(次の検査で用紙が変わっていたらNGですけど・・・)
上記3点セット、車検証、納税証明証、予約の受付番号のプリントアウト、自賠責保険、バイクの整備記録簿など諸々バインダーに挟んだ状態で受付の担当の方に渡しました。そのまま受け取って確認後押印して戻してくれます。
受付窓口は7番になります。

ここまでを受付時間終了までに終わらせるのが原則です。
多少遅れても大丈夫でした。
さてそれではユーザー車検のクライマックスともいえる検査ラインでの実検査にGOです。
7.検査ラインの実検査
バイクは二輪専用検査ラインに並びます。

前に4人くらい並んでいた程度で比較的空いていました。
ここでも検査官にバインダーセットを渡して書類の確認してもらいます。
その後問題がなければ検査官の指示通りにウインカー、クラクション、ブレーキランプ、などを操作し動作確認してもらいます。
ここで6回目にして初めてですがマフラー交換してますね~音測りましょうか。
と言われ実測されました。
測定装置はこんな感じです。
2500回転までエンジンを回すよう指示され排気音を測定されました 結果96dBで合格です。
この単車は登録がH12年で騒音の規定が99dBです。そして排気ガス規制の適用外なので
カスタムベースとしてはオイシイ年式です。

初めて実測されたのでヒヤヒヤしました・・・
そしていよいよ自分の番が回ってきました。
初めはブレーキ、スピードメーター検査です。
検査装置の手前右側にスピードメーターが前輪で測定するか後輪で測定するかを選択するボタンがあるので対応するほうを押します。
この単車は後輪なので後輪ボタンを押します。
過去の検査で前の人の設定をそのまま変えずにラインに入ってしまい前輪をグルグル回されてしまった苦い経験があります。
事前にご自分のバイクがどちらかを調べておいてください。

このボタンさえ間違えなければ表示の指示通りにブレーキ踏んだり、メーターが40㎞になったら測定装置から足を外すとかしていると終了します。問題がなければ結果を記録する装置に先ほどの自動車検査票1の左側をガチャっと音がするまで奥に差し込みます。
すると合格マークが押印されます。

そしていよいよ鬼門のヘッドライト光軸です。
前回何度通してもNGとなり予備車検場にお世話になりましたので・・・
多少不安だったので写真を撮る余裕はありませんでした。
バイクを所定の位置まで進めるように指示されますが線にタイヤの先頭を合わせるのではなく接地点を合わせます。
検査中はエンジンをふかし気味にして少しでも光量を稼ぎます(あまり意味はないらしいですが・・・)
今回は無事合格です。
前の検査同様に記録マシンに押印してもらい検査ラインは終了です。
次の検査は排ガスのようなのでこの単車は対象外ですのでそのまま突っ切ります。
対象のバイクはマフラーのなかに検査棒をいれて検査するようですね。

最後に人がいるブースに結果をもって行き最終合格印を押してもらいます。

これで検査ラインは終了です。
今回は無事に一発で通せました。
この動画は横浜と少し違いますが疑似体験できて良いです。
検査ラインを後にして・・・

検査結果をもって再び②の建物に向かいます。
結果は7番のトレイに先ほどの書類3セット+車検証を提出する。

名前が呼ばれてNew車検証とNewシールが貰えればすべて完了~
お疲れさまでした

検査ラインの検査官に”初めてのユーザー車検です”と伝えるとヒマであればずっと付き合ってスイッチ操作や記録をしてくれます。
混んでいるときは迷惑になるので自分でできるようにシミュレーションしておきましょう。
【整備はしっかりと!】
ショップに出すと24ヶ月点検、オイル交換、消耗品交換、車検代行手数料などで5~10万コースになりますが
自分で行えば2万円でおつりが来ます。
但し、オイル交換や必要な点検整備は自分でしっかり行う前提ですのでお忘れないように!
私も車検2回に一度(3回に一度?)はショップに持って行き点検をやってもらうようにしています。
不幸にして検査ラインNGになった場合は自分で光軸を治すのは至難の業ですので
素直に予備車検場に向かわれることをお勧めします(バイクで5分くらいの場所にあります)。
その日のうちなら何回でも検査ラインを通れます(NGになった項目のみできます)。
2回くらいは自分でチャレンジしてもいいですが・・・光軸は・・・無理っ!
あとヘルメットは邪魔なのでバイクに括り付けておくと良いでしょう。
腕にひっかけてやりましたが邪魔でした・・・
終了後、すぐ近くにあるIKEAによってコーヒーのミルクフォーマを3個買ってきました。
午後からはTAKUのピアノの発表会に行きました。
ドビュッシーの月の光を華麗に弾いていました。親ばか目線ですがカッコよかったです、女子にモテそう・・・

自分、楽器できないので羨ましいです~

にほんブログ村
1.継続車検の予約
・神奈川陸運支局のHPにアクセスする。
・左のメニューの検査手続きをクリックすると
検査の予約は自動車技術総合機構の予約システムからをクリックして予約システムに飛んでください。そこで新規アカウントを作って(簡単な手続き)検査を受ける日の予約を入れます。予約が完了すると予約システムから予約番号が書いてあるメールがくるのでそれをプリントアウトしてもって行きましょう。
【当日必要なもの】
・車検証
・自動車税納税通知書/領収書
・自賠責保険の証書
・点検整備記録簿(バイク購入時に冊子でもらえました なければこちらのリンクからダウンロードできます)
・上記を挟んでおくバインダー(書類を持って回るのであると便利)
・工具(ちょっとした修正ができるくらいのもの)
・印鑑(変更などがあった時の為 使ったことはない)
・現金
・予約システムから送られてきたメールをプリントアウトしたもの
2.神奈川陸運支局へGO
そしていよいよ出発です。
書類を揃えて記入してから受付するので受付終了時間の30分前には到着すると良いでしょう。
初めてなら1時間前くらいについているとゆとりをもって望めます。

適当な場所にバイクを駐車して③の建物に向かいましょう。
門を入って右側に建物が並んでおり③とビルに書いてありますので迷いようがありません(w

3.自賠責保険の更新手続き
③の建物の右下に代書と書いてある窓があります。
このスペースが自賠責保険の窓口もやっています。

ここで自賠責保険を2年延長する手続きを行い保険証をバインダーに挟んでおきます(受付時とか何かと確認されます)。
あくまで私のルーチンの紹介をしています。敷地の外にも沢山代書屋、保険窓口がありますのでお好きなところでどうぞ。
因みに書類の記入(代書)もやってくれます、2,500円くらいだそうですが継続なら自分で簡単にできますのでチャレンジしましょう。
ここで掛かった費用自賠責保険代13,640円
4.書類と印紙の購入
次に③の建物の右のほうの入り口から入ります。

ここで印紙を購入します。

ここで掛かった費用は
重量税印紙:4,600円
検査登録印紙:400円
審査証紙:1,300円
--------------------------------
合計:6,300円 (大型バイクの場合)
印紙を購入したらその左側の受付窓口で下記の用紙セットを購入します。
この3枚1セットで20円です。
・自動車検査票1(表)/自動車検査票2(裏)
・自動車重量税納付書
・継続審査申請書
今回は次の車検用に事前に記入してスムーズに臨めるようにと書損じたときの為に5セット購入しました。
費用は20円x5セットで100円です。
これ以外の費用は発生しません。
大型バイクのユーザー車検でかかる費用の合計は19,960円です。
通すだけなら最低この金額で通せます(用紙の予備は無で)。
③の建物には印紙を濡らすスポンジが置いてありますのでここで印紙を貼ってしまうことをお勧めします(他の建物だとツバつけて貼るしかない)
自動車検車票1の右の手数料納付書の下のマスに1,300円の印紙と400円の印紙を貼り付けます。
自動車重量税納付書の下のほうに4,600円の印紙【4,000+600)を貼り付けます。
(貼る組み合わせを間違えないように注意、印紙のレシートに金額の内訳があるからそれを見ながら貼りましょう)
5.納税証明
このあと2年前は③の建物の左側にある④の建物に入って自動車税の納税証明確認をしてもらうルーチンがありました。
今回④に入って納税通知書と領収書を窓口に出したところ 去年からこちらでは行っておりません継続審査受付で提出してください。と言われてしまいました。
もう④に来なくていいんですね~ 一つ工程が省けて得した気分です。
6.継続検査受付
そしていよいよ継続検査の受付のある②の建物に向かいます。
③の建物のトイメンの80mくらい離れたところで写真の右奥の2階建です。建物の上のほうも②とありますね。

ここで購入した3枚の用紙に必要事項を記入して受付を行います。
記入スペースに記載例が書かれていますので迷う部分はないと思います。
基本現行の車検証の記載内容を転記する(車体番号とか登録番号とかetc.)。
走行距離を記入する部分があったので予め調べておきましょう。
・自動車重量税納付書

記入例を見ながら書けばOK
今は詳しく解説されているブログが多くて助かります。こちらなど大変参考になります。
・自動車検査票1(表)

走行距離記入する箇所あります。
車検証と記入例を見ながら記入しましょう。
この一枚は後程検査ラインで合格の際にスタンプを押す用紙となります。
自動車検査票2(裏)

これも車検証に記載されている部分を記入すればOKでした。
ホイールベースの値、タイヤの大きさなどは空欄で出しましたが何も言われおりません。
・継続審査申請書

記入例を見ながら書けばOK
鉛筆書き指定のところがあるのでボールペンで書かないように・・・
記入するのに慣れないと30分くらいは掛かってしまいますので早めに到着したほうがよいですね。
家で記入していけば更に楽になりますので2年後の為に用紙は2セット以上買っておきましょう。
(次の検査で用紙が変わっていたらNGですけど・・・)
上記3点セット、車検証、納税証明証、予約の受付番号のプリントアウト、自賠責保険、バイクの整備記録簿など諸々バインダーに挟んだ状態で受付の担当の方に渡しました。そのまま受け取って確認後押印して戻してくれます。
受付窓口は7番になります。

ここまでを受付時間終了までに終わらせるのが原則です。
多少遅れても大丈夫でした。
さてそれではユーザー車検のクライマックスともいえる検査ラインでの実検査にGOです。
7.検査ラインの実検査
バイクは二輪専用検査ラインに並びます。

前に4人くらい並んでいた程度で比較的空いていました。
ここでも検査官にバインダーセットを渡して書類の確認してもらいます。
その後問題がなければ検査官の指示通りにウインカー、クラクション、ブレーキランプ、などを操作し動作確認してもらいます。
ここで6回目にして初めてですがマフラー交換してますね~音測りましょうか。
と言われ実測されました。
測定装置はこんな感じです。
2500回転までエンジンを回すよう指示され排気音を測定されました 結果96dBで合格です。
この単車は登録がH12年で騒音の規定が99dBです。そして排気ガス規制の適用外なので
カスタムベースとしてはオイシイ年式です。

初めて実測されたのでヒヤヒヤしました・・・
そしていよいよ自分の番が回ってきました。
初めはブレーキ、スピードメーター検査です。
検査装置の手前右側にスピードメーターが前輪で測定するか後輪で測定するかを選択するボタンがあるので対応するほうを押します。
この単車は後輪なので後輪ボタンを押します。
過去の検査で前の人の設定をそのまま変えずにラインに入ってしまい前輪をグルグル回されてしまった苦い経験があります。
事前にご自分のバイクがどちらかを調べておいてください。

このボタンさえ間違えなければ表示の指示通りにブレーキ踏んだり、メーターが40㎞になったら測定装置から足を外すとかしていると終了します。問題がなければ結果を記録する装置に先ほどの自動車検査票1の左側をガチャっと音がするまで奥に差し込みます。
すると合格マークが押印されます。

そしていよいよ鬼門のヘッドライト光軸です。
前回何度通してもNGとなり予備車検場にお世話になりましたので・・・
多少不安だったので写真を撮る余裕はありませんでした。
バイクを所定の位置まで進めるように指示されますが線にタイヤの先頭を合わせるのではなく接地点を合わせます。
検査中はエンジンをふかし気味にして少しでも光量を稼ぎます(あまり意味はないらしいですが・・・)
今回は無事合格です。
前の検査同様に記録マシンに押印してもらい検査ラインは終了です。
次の検査は排ガスのようなのでこの単車は対象外ですのでそのまま突っ切ります。
対象のバイクはマフラーのなかに検査棒をいれて検査するようですね。

最後に人がいるブースに結果をもって行き最終合格印を押してもらいます。

これで検査ラインは終了です。
今回は無事に一発で通せました。
この動画は横浜と少し違いますが疑似体験できて良いです。
検査ラインを後にして・・・

検査結果をもって再び②の建物に向かいます。
結果は7番のトレイに先ほどの書類3セット+車検証を提出する。

名前が呼ばれてNew車検証とNewシールが貰えればすべて完了~
お疲れさまでした

検査ラインの検査官に”初めてのユーザー車検です”と伝えるとヒマであればずっと付き合ってスイッチ操作や記録をしてくれます。
混んでいるときは迷惑になるので自分でできるようにシミュレーションしておきましょう。
【整備はしっかりと!】
ショップに出すと24ヶ月点検、オイル交換、消耗品交換、車検代行手数料などで5~10万コースになりますが
自分で行えば2万円でおつりが来ます。
但し、オイル交換や必要な点検整備は自分でしっかり行う前提ですのでお忘れないように!
私も車検2回に一度(3回に一度?)はショップに持って行き点検をやってもらうようにしています。
不幸にして検査ラインNGになった場合は自分で光軸を治すのは至難の業ですので
素直に予備車検場に向かわれることをお勧めします(バイクで5分くらいの場所にあります)。
その日のうちなら何回でも検査ラインを通れます(NGになった項目のみできます)。
2回くらいは自分でチャレンジしてもいいですが・・・光軸は・・・無理っ!
あとヘルメットは邪魔なのでバイクに括り付けておくと良いでしょう。
腕にひっかけてやりましたが邪魔でした・・・
終了後、すぐ近くにあるIKEAによってコーヒーのミルクフォーマを3個買ってきました。
午後からはTAKUのピアノの発表会に行きました。
ドビュッシーの月の光を華麗に弾いていました。親ばか目線ですがカッコよかったです、女子にモテそう・・・

自分、楽器できないので羨ましいです~

にほんブログ村
Posted by すけさん at 13:02
│バイク関連